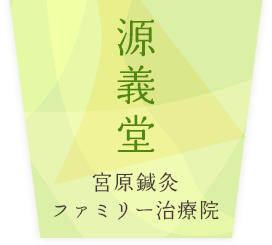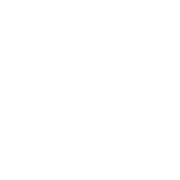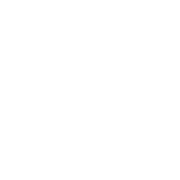インスリンと膵臓、小腸
インスリンというと糖尿病を連想しますけれど、実は普通にすい臓から分泌されるホルモンです。すい臓のランゲルハンス島にある3種の細胞αβδが絶妙のコンビネーションで血糖値をコントロールしています。
α細胞は血糖値を上げるグルカゴンを分泌します。
β細胞は血糖値を下げるインスリンを分泌します。
δ細胞はソマトスタチンによって双方のバランスをとっています。
ニユートン7月号の表現をかりれば、これら三つの細胞がそれぞれ情報交換を行い、適切な時に適切な量のホルモンが分泌されることで、体内の血糖値は厳密に制御されているのです。
血糖値が上がると、β細胞がグルコースを細胞内に取り込み分解します。その刺激で更にインスリンが分泌され、更に血糖値を下げる方向に働きます。
面白いのは小腸の蠕動運動によって小腸の細胞からGLP -1等のホルモ東洋医学でいうとンが分泌され、すい臓に働きかけ、インスリン分泌が増加するという点です。
東洋医学でいうと、火である小腸が土のすい臓の働きを促進させるのはまさに火生土の相生関係であります。小腸の活性化の為には腹部の按腹はもちろんですが、笑いも大切です。